
不動産相続
不動産相続、
あなたにとって最良の選択を
大切な人から受け継いだ不動産。その相続は、喜びとともに、複雑な手続きや税金、そして将来への不安も伴うものです。
「どうすればいいのかわからない」「家族と意見が合わない」「税金対策はどうすればいいの?」
そんな悩みをお持ちのあなたへ、札幌市の不動産会社アルズリライトが不動産相続の基礎知識からスムーズな手続き、そして将来を見据えた活用方法まで、わかりやすく解説していきます。
- お急ぎの方はこちら011-699-6001火曜・水曜も受付中!
- 友だち追加でらくらくカンタン相談
- 24時間受付&こっそり無料査定・お問い合わせ
- トップページ
- 不動産相続
スムーズに進めるための相続手続き

不動産の相続手続きは複雑で、様々な書類を用意しなければいけません。特に 2024 年 4 月から相続登記が義務化されたため、早めの対応が求められます。
相続が発生した場合は、以下の流れで書類の準備や手続きを進めましょう。
相続完了までの流れ
- STEP.01
- 遺言状の確認
- まずは、被相続人の遺言状があるかを確認します。遺言状がある場合は内容どおりに従い、ない場合は遺産分割協議によって不動産を含むすべての財産の分割方法を相続人全員で話し合います。
- STEP.02
- 相続人の確定
- すべての相続人を知るには、被相続人の戸籍謄本が必要です。戸籍謄本には過去の結婚歴や子供などの情報がすべて記載されているため、法定相続人を知ることができます。
- STEP.03
- 相続財産の確認
- 相続財産に不動産がある場合は、固定資産税評価証明書など使いながら評価額を把握します。ただし、不動産の評価額は複雑なため、専門家への依頼がおすすめです。
- STEP.04
- 遺産分割協議の実施
- 遺言状がない場合、相続人全員で「どの財産を「誰が」「どれくらい」「どのように」相続するかを協議します。相続には、相続人全員の合意が必要です。全員からの合意が得られれば、協議内容を遺産分割協議書に記載します。
- STEP.05
- 相続登記の申請
- 不動産を相続した場合、相続登記が必須です。2024 年 4 月から相続登記が義務化されたため、なるべく早いタイミングで相続登記の申請を行いましょう。
- STEP.06
- 相続税の申告・納付
- 相続には、相続税がかかります。被相続人が亡くなった日から 10 か月以内に、相続税を納付する必要があります。
不動産相続にかかる税金や費用

不動産を相続すると、以下の税金や費用がかかります。何にどれくらいかかるかを事前に把握し、計画的に相続準備を行いましょう。
相続税
不動産だけでなく、相続した資産すべてにかかる税金が相続税です。ただし、相続税には基礎控除額が決められており、基礎控除額を上回る場合にのみ相続税の支払い義務が発生します。
【相続税の基礎控除額】
3,000 万円+600 万円 × 法定相続人の数
基礎控除額を引いた課税遺産総額によって、以下のように税率が異なります。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 課税遺産総額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000 万円以下 | 10% | 0 円 |
| 1,000 万円超から 3,000 万円以下 | 15% | 50 万円 |
| 3,000 万円超から 5,000 万円以下 | 20% | 200 万円 |
| 5,000 万円超から 1 億円以下 | 30% | 700 万円 |
| 1 億円超から 2 億円以下 | 40% | 1,700 万円 |
| 2 億円超から 3 億円以下 | 45% | 2,700 万円 |
| 3 億円超から 6 億円以下 | 50% | 4,200 万円 |
| 6 億円超 | 55% | 7,200 万円 |
固定資産税・都市計画税
不動産の相続には、固定資産税と都市計画税もかかります。これらの税金は市区町村によって税率が異なり、安城市の場合次のとおりです。
| 税金 | 税率 |
|---|---|
| 固定資産税 | 課税標準額 ×1.4% |
| 都市計画税 | 課税標準額 ×0.3% |
ただし、土地・建物・償却資産が以下に満たない場合は、固定資産税は加算されません。
- 土地:30 万円
- 建物:20 万円
- 償却資産:150 万円
登録免許税
2024 年 4 月から義務化された相続登記にかかる税金で、固定資産税評価額の 0.4% かかります。相続登記を司法書士に依頼する場合は、登録免許税のほかに司法書士費用も発生します。
譲渡所得税
相続した不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。譲渡所得税は、売却金額から不動産を相続した際にかかった費用と売却にかかった費用を差し引いた額で計算します。ただし、相続税は費用として認められません。
【不動産の相続手続きに必要な費用まとめ】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 相続税 | 基礎控除(3,000 万円+600 万円 × 法定相続人の数)を超えると発生 |
| 固定資産税 | 課税標準額 ×1.4%(安城市の場合) ※1 |
| 都市計画税 | 課税標準額 ×0.3%(安城市の場合) ※1 |
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の 0.4% ※2 |
| 譲渡所得税 | 売却金額 - 相続・売却にかかった費用で計算(相続税を除く) |
※1:課税評価額が土地 30 万円・建物 20 万円・償却資産 150 万円に満たない場合は課税されない
※2:相続登記の申請を司法書士に依頼すると別途費用がかかる
 不動産を相続してから3年以内に売却
不動産を相続してから3年以内に売却
することで、税制上大きなメリットが!

相続不動産の売却には「取得費加算の特例」が適用され、相続税の一部を譲渡所得から控除できるため、課税額を大きく抑えることが可能です。この特例は「相続開始の翌日から3年10か月以内」に売却することで適用されます。相続後に不動産売却を検討している方は、売却タイミングが節税に直結するため、早めの検討が重要です
不動産相続、知っておきたい 8 つの注意点
不動産の相続には、判断や対応が複雑な問題が多くあります。ここからは、不動産を相続する際の注意点と対応方法について紹介します。
相続人が複数いる
相続人が複数いる場合、遺産分割協議を行い、分割方法を選択します。不動産を分割する方法には、以下の 4 つがあります。
| 分割方法 | 内容 |
|---|---|
| 換価分割 | 不動産を売却し、売却代金を分割する |
| 現物分割 | 一方が不動産を所有し、もう一方が不動産以外の財産を所有する |
| 代償分割 | 一方が不動産を所有し、もう一方に代償金を支払う |
| 共有分割 | 不動産を共有名義で所有する |
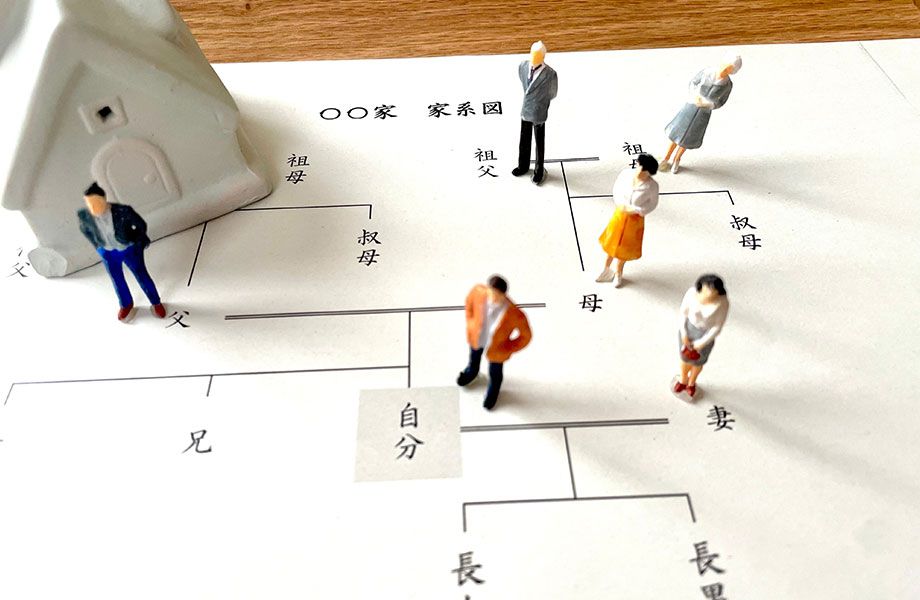
分割方法の決定には、相続人全員の合意が必要です。簡単に決まらない場合は、専門家への相談も手段の一つです。
不動産を相続したくない

相続したくない場合、相続放棄を家庭裁判所に申請することができます。相続を知った 3 ヶ月以内であれば申請が可能です。相続土地国庫帰属制度 を利用して、土地を国に引き取ってもらう選択肢も選べます。
家が借地

借地権付きの家を相続する場合、地主との契約更新が必要になるケースがあります。地主と事前に相談し、売却や更新について協議を行うことが重要です。借地権を相続すると、家を財産として所有できます。相続税は建物と借地権の両方にかかり、土地の価格に借地権割合をかけた金額となります。
親が認知症になる前に相続対策をしたい

認知症になると財産管理が難しくなるため、認知症になる前に家族信託や任意後見制度を活用することがおすすめです。
家族信託とは
認知症などの理由で親が財産を管理できない際に、家族に財産管理の権利を託す制度のことです。遺言では不可能な、「次の次の世代」の相続人まで指定できます。
任意後見制度とは
親が認知症などになる前に相続の任意後見人を決めておく制度のことです。任意後見人になると、被相続人の同意がなくても不動産売却などの手続きができます。
相続発生前に不動産価値を把握する

不動産の価値を相続前に把握しておくことで、相続税の対策や遺産分割の計画が立てやすくなります。不動産会社の無料査定を利用し、事前に不動産価値を把握しておきましょう。
相続発生前に売却しておいたほうが良い不動産

活用予定のない家は、相続前に売却することで税金や管理コストを削減できます。特に、以下の特徴が当てはまる不動産は、相続発生前の売却がおすすめです。
- 不動産の価格が高騰している
- 市場での需要が低い
- 相続税が軽減できる「小規模宅地等の特例」などが使えない
大切な不動産が「負動産」とならないよう、早めの決断を行いましょう。
生前贈与をしたい

生前贈与については、一概には言えませんが、贈与税の負担が大きくなることが多いため、相続のほうが有利になるケースもあります。ただし、「相続時精算課税制度」や「贈与税の非課税枠」などを活用すれば、生前贈与の方が節税になる場合もあります。
相続時精算課税制度とは
60歳以上の親から18歳以上の子どもへの贈与に使える制度で、2,500万円までの贈与に贈与税がかからず、相続時にまとめて精算される仕組みです。ただし、一度適用すると「暦年課税(「贈与税の非課税枠)」は使えなくなるため注意が必要です。
贈与税の非課税枠とは
贈与税には年間110万円までの非課税枠があり、この金額以内なら税金はかかりません。また、住宅取得や教育資金など特定の目的に使う場合は、条件付きで1,000万円以上が非課税になる制度もあります。
家の相続には信頼できる不動産会社が必要

相続は、大切な人からの思いが形になったものです。相続した不動産を売却・活用する際は、信頼できる不動産会社を選び価値を最大限に生み出しましょう。
当社では、相続の専門家と連携し適正な査定と手続きのサポートを提供しています。不動産相続にお困りごとがある方は、ぜひ一度当社までご相談ください。
不動産相続のトラブル事例
不動産相続では、仲のよい家族間でもトラブルに見舞われるケースが多いです。札幌市内でも不動産トラブルは多発しているため、具体的な事例と解決策を確認しておきましょう。アルズリライト株式会社は、弁護士や司法書士といった専門家と提携し、諸問題を解消しながら不動産売却を成功へと導いています。
亡くなった父親に愛人と隠し子がいた

状況
札幌市在住のA様は、夫が亡くなったことに伴い、市内の実家を相続することになりました。相続人は配偶者である妻のA様だけと考えていたのですが、夫には愛人と隠し子がいたことが発覚したのです。愛人は不動産などの遺産の一部を相続することを望んでいますが、複雑な関係性でもあるため、相続が進展しません。なお、遺言書は残されていませんでした。
解決策
- 愛人は法定相続人ではないため、遺言書がなければ遺産を相続させる必要がない
- 隠し子は夫と血のつながりがあるものの、認知されていなければ相続させる必要がない
解説
遺産を相続できる権利を持っているのは法定相続人だけです。愛人は法定相続人に含まれないため、愛人に遺産を渡す必要はありません。
一方の隠し子は夫と血がつながった血族のため、被相続人に該当します。そのため、隠し子は遺産相続が可能です。ただし、相続できるのは認知されている子どもに限定されます。このケースでは認知されていなかったため、隠し子も遺産を相続できません。
しかし、夫が遺言書を残しており、遺言書に「愛人や隠し子に遺産を相続させる」といった旨が記されている場合は、遺言書のとおりに相続を行う必要があります。この場合、配偶者は最低限の取り分である「法定相続分」の請求が可能です。
相続した実家が老朽化していて売却できない

状況
B様は札幌市内の実家を相続しました。しかしB様には持ち家があり、実家は勤務地からも遠いため、実家に住み替える予定はありません。しばらく実家を空き家として放置していましたが、固定資産税や管理費がかかるため、B様は売却を決意しました。ところが実家は老朽化して資産価値を落としており、買主様が見つからずに困っています。
解決策
- 空き家に詳しい不動産会社に相談する
- 仲介売却と並行して不動産買取の利用を検討する
解説
老朽化した空き家は買主様が見つかりにくく、取り扱いを拒否する不動産会社もあります。リフォームやリノベーションをしなければ住めなかったり、遺品などの残置物が多かったりすることが、老朽化した家を売却しにくい理由です。
この場合は、空き家や相続に強い不動産会社に相談しましょう。リフォーム業者や解体業者、遺品整理業者などと提携する不動産会社を利用すると、老朽化した不動産でもスムーズに売却できる可能性が高いです。
一般から買主様が見つからない場合は、不動産会社が直接購入する不動産買取の利用も検討しましょう。仲介売却が不調な場合、指定した期間内に不動産買取へと移行する「買取保証付き仲介」を利用できる不動産会社の利用は、特におすすめできます。
相続人の1人が認知症で意思の疎通を図れない

状況
札幌市にお住まいのC様は、お兄様のD様と実家を相続することになりました。C様は売却を望んでいますが、D様が認知症を発症しており、意思の疎通を図れません。C様は不動産会社に相談しましたが、D様の意思がわからない状態では売却ができないと言われてしまい、困っています。
解決策
- 司法書士や弁護士と提携する不動産会社に相談する
- 成年後見制度を利用する
解説
相続人が認知症を発症している場合は、成年後見制度を利用すると良いでしょう。成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した方に代わり、家庭裁判所が選んだ成年後見人が不動産売却などを代行する制度です。
D様は重度の認知症のため、相続した不動産をどのように扱うか判断できません。しかし、成年後見制度を利用してC様が成年後見人になることにより、C様の判断で不動産売却ができるようになります。
このようなケースでは、弁護士や司法書士といった法律の専門家によるサポートが必要なため、士業と提携する不動産会社への相談をおすすめします。不動産売却と成年後見制度の相談窓口を一本化できるため、効率よく手続きを進められるでしょう。
不動産相続でよくあるご質問
「相続をされる側」の方からよくあるご質問
- Q不動産相続は、相続を「する側」の被相続人、「される側」の相続人によって、重視すべきポイントが異なりますが、何もわからないです。訊きたいこともまとまっていないですが相談できますか?
- Aもちろんです!ご安心ください。 「受ける側」の立場から、不動産相続について相談したいことはたくさんあると思います。当社は、お客様の立場に立った丁寧なサポートを心がけていますので、どうぞお気軽にご相談ください。
- Q不動産相続で特に難しい手続きはありますか?
- Aはい、いくつかあります。 例えば、放置すると相続人が変わったり、本来の相続人とは別の第三者が遺産相続に関与したりするリスクがあります。そのため、名義変更をスムーズに行うことが重要です。
- Q不動産相続で最初にやるべきことは何ですか?
- A多くの手続きに期限があるため、相続人同士でスケジュールを共有し、協力して進めることが大切です。 当社は、お客様の不動産相続をあらゆる観点からサポートいたします。
- Q遺言書の内容は絶対ですか?
- A遺言書の内容によっては、相続人に不利益が生じる場合もあります。 例えば、申告納税の負担が増える可能性も。遺産分割を検討することで、相続税の納付額を減らせることもあります。
- Q認知症の相続人がいる場合、特別な対応が必要ですか?
- Aはい、必要です。 遺産分割協議では、相続人の意思に基づく署名捺印が必要です。しかし、相続人の認知機能に問題がある場合、適切な判断ができない可能性がございます。その場合は成年後見制度をご利用いただき、遺産分割協議に成年後見人が参加。当該相続人の代わりに署名捺印することで、遺産相続を進めることが可能です。
- Q空き家になった実家を相続します。活用法などを相談できますか?
- Aぜひご相談ください。 深刻化する “空き家問題” から、2015 年 5 月に「空き家対策特別措置法(2015 年)」が施行されました。管理状態の悪い空き家を放置すると、行政の指導が入ったり、固定資産税が最大 6 倍に膨れあがる可能性があります。空き家の放置には、デメリットしかございません。当社にご相談いただければ、不動産相続および空き家活用について、詳しくお話させていただきます。
「相続をする側」の方からよくあるご質問
- Q節税対策で賃貸物件を建てたいのですが、具体的なアドバイスをもらえますか?
- Aぜひご相談ください。 空き家の利活用をはじめとする「不動産の収益物件化」も得意としています。各分野の専門家と連携し、賃貸物件の建築から運用まで、ワンストップでサポートいたします。
- Q相続税の申告期限を教えてください
- A「相続人が相続開始を把握した日から 10 ヵ月以内」が法律上の申告期限です。 しかし、「被相続人の死亡後から 10 ヵ月以内」が実質的かつ実務上の期限となります。
- Q相続税に時効はありますか?
- A相続税には、「除斥期間」という名の実質的な時効が存在します。 法定申告期限から 5 年間経過した場合、相続税の納付義務がなくなります。ただし、税務署から連絡があった際は例外です。
- Q相続の流れを教えてください
- A一般的には、遺言書の有無を確認します。 遺言書が見つかった場合、家庭裁判所で検認を受けて開封します。なお、公正証書遺言の場合、家庭裁判所の検認は不要です。続いて不動産などの相続・法規・限定承認などを決定し、戸籍謄本などの必要書類を収集。準備が整い次第、遺産分割協議を実施します。協議成立の場合は、遺産分割書の作成および納税申告・納付、不成立の場合は、調停・裁判に移行します。
- Qどのような資産に相続税が課せられるのですか?
- A原則、相続資産額が基礎控除額を上回った場合のみ、相続税が課せられます。 なお、相続人が配偶者の場合、軽減措置により資産額 1 億 6000 万円分までは非課税となります。
- Q不動産相続について家族間で揉めています。すぐに相談できますか?
- A早急にご相談ください。 “争族(そうぞく)” と比喩されるほど、相続に家族・親族間トラブルはつきものです。相続問題は、何らかの対策を講じない限り長期化し、さらなる関係者の介入も考えられます。長引くほどに申告化するばかりです。弁護士等、法律の専門家の紹介を含め、当社ではお客様一人ひとりのお悩みに寄り添い、問題解決に向けてサポートいたします。
当社について
- Q不動産相続の対応エリアを教えてください
- A当社は札幌市を中心に不動産相続対策を行っております。 対象エリアに物件があり、遠方にお住まいの方は、オンラインでのお打ち合わせもご検討ください。
- Qどのようなスタッフが対応してくれますか?
- A不動産に精通する有資格者が直接対応いたします。 相続問題と不動産は、切っても切れない関係にございます。不動産の専門知識はもちろん、相続問題の解決実績を有するスタッフが対応することで、お客様のお悩みを解決いたします。

